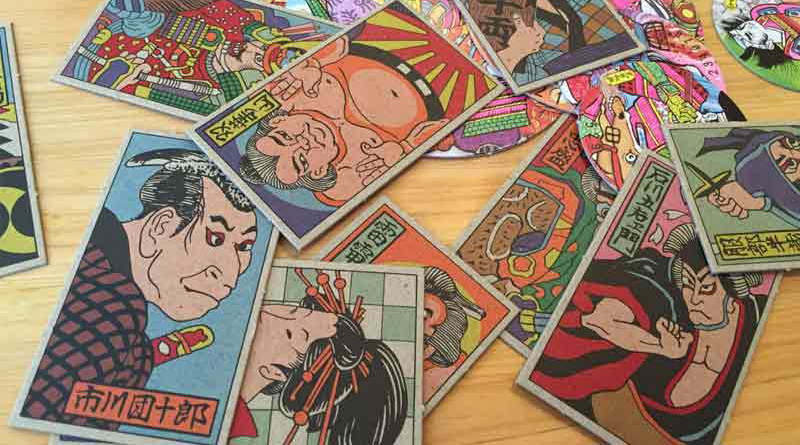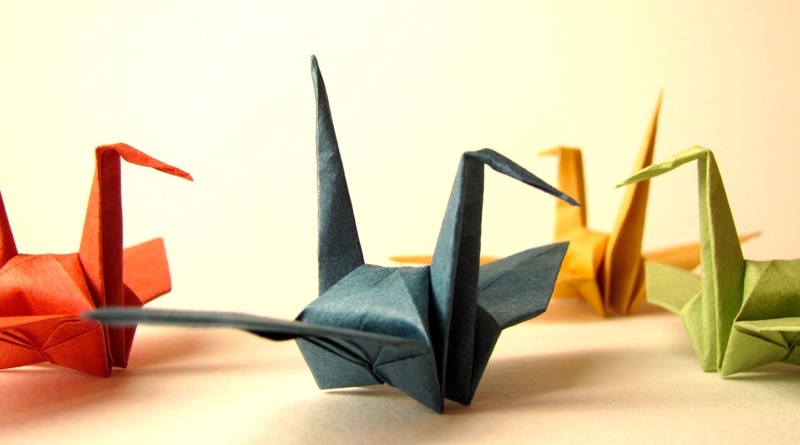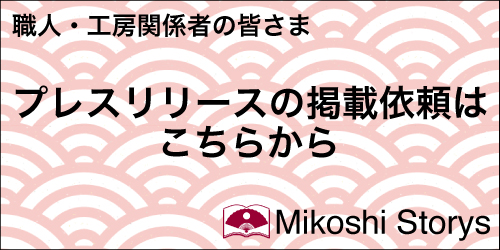的を射る、と聞いて何が思いつきますか?
日本には、「騎射(きしゃ)」という伝統的な武芸があります。
今回は、古来から伝わる儀式の一つでもあり、観客を魅了してやまない「流鏑馬(やぶさめ)」についてご紹介します。
◎名前の由来
疾走する馬の上に乗った状態で矢を射ることから「矢馳せ馬」と呼ばれていたものが、時の経過とともに「やぶさめ」と呼ばれるようになりました。
◎歴史
時代は平安時代までさかのぼります。流鏑馬は、笠懸(かさがけ)と犬追物(いぬおうもの)と共に「騎射三物」の一つとし、馬を走らせた状態で的を射る朝廷儀式の一つとして盛んに行われていました。
◎馬場
会場、つまり馬場は長さ2町(約218メートル)、幅1丈(3.03メートル)の中を馬走します。
的は3箇所立て、一つ目的までは48丈、一つ目と二つ目の間は38丈、二つ目と三つ目の間は37丈の間隔をあけます。的と馬走の間は3丈を基本としますが、5丈や7丈であることもあります。
◎掛け声
流鏑馬では掛け声が欠かせません。
射手が的を射る前に声をかけます。
一の的の前では「インヨーイ」
二つ的の手前で「インヨーイインヨーイ」
三つ的手前では「インヨーイインヨーイインヨーーイ」
とそれぞれ違うトーンで掛けます。
これらの掛け声は、「陰陽」が元となっています。
◎現在の流鏑馬
かつては、朝廷儀式の一つでしたが、今や日本全国の神社で祭事として行われています。
近年は、停止させた馬の上から的を狙う「子ども流鏑馬」を催している神社もあります。
「やぶなび」で開催場所や時期を確認し、
是非一度足を運び、疾走する馬の上から次々に的を射る迫力を間近で見てみませんか?
フォローしていただくと、更新情報を受け取ることができます。