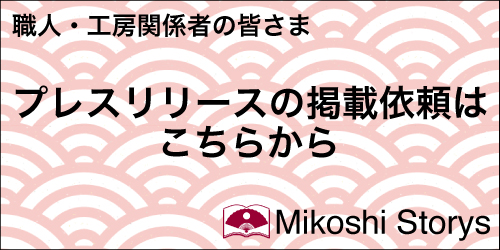変わりやすい春の天候が安定しだす時期に、「穀雨(こくう)」という二十四節気の一つがあるのをご存知ですか?新芽を育てる春雨が降り出すこの頃を意味する穀雨とは、どういったものかご紹介します。
時期や由来
4月20日頃、また、この日から立夏前日までの期間が穀雨になります。春の雨が百穀を潤すという意味を持つ二十四節気の一つで、春の最後の節気です。秋に収穫する穀物の種まきシーズンとなり、穀雨を目安として田畑の準備が始まります。穀雨の終わりには八十八夜があります。
旬の食材

「夏も近づく八十八夜♪」で多く知られている、茶摘みの時期を迎えます。この頃から6月くらいまでに採られた新茶は初物として重宝されています。江戸時代、将軍家の御用達とされた宇治のお茶は、はるばる江戸城に運ばれていました。この様子は「お茶壷道中」と言われ、庶民はひれ伏し大名は道を譲っていたそうです。他にも枇杷(びわ)やホタルイカがこの時期の旬となっています。
春の雨の名前
この時期に降る雨の特徴によって呼び方があります。
百穀春雨(ひゃくこくはるさめ)
穀物の芽を出させる穀雨の頃に降る雨
春時雨(はるしぐれ)
降ったりやんだりする春の気まぐれな雨
杏花雨(きょうかう)
杏の花が咲く、清明の頃に降る雨
菜種梅雨(なたねつゆ)
菜の花の咲いている時期に降り続く雨
紅の雨(くれないのあめ)
ツツジやシャクナゲ、桃など、紅の花が咲く頃の雨
催花雨(さいかう)
花の咲くのを催促するように降る雨

〜おわりに〜
これから迎える夏の暑さ対策として、緑のカーテン作りを始めるのもこの時期が良いそうです。自然を意識したものを生活を取り入れるのもいいですよね。
参考:
春夏秋冬を楽しむくらし歳時記(成美堂出版)