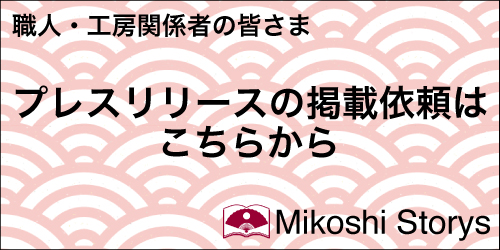寒さが厳しくなってきて、マフラーをしまってあった押し入れから引っ張りだしてきた人も多く、街ではイルミネーションが目立ち、これから見に出かけることも多いのではないだろうか?
寒い時は手袋やマフラーを身につけ、時にはホッカイロを持って外出するだろう。
では、家にいるときはどうやって暖を取っているだろうか?
今回は日本で昔から愛されている室内防寒グッズを3つご紹介しよう。
①股引(ももひき)
股引は伝統的なボトムスである。
男性用下着としても使用されており、女性が使用するスパッツやレギンスの男性版として認識されることも少なくはない。
保温の為にズボンの下などに履く男子用下着である傍ら、祭りなどで神輿の担ぎ手の衣装としても使用されている。
近年人気のあるステテコのベースとなったとも言われており、下半身の保温効果を求めるなら股引かもしれない。
②湯たんぽ
中にお湯を入れて体を温めるために古くから使用されている湯たんぽ。日本には室町時代に中国の唐から伝えられ、当時は陶器製であったが、大正期以降から金属製になった。

湯たんぽは安く、持ち運びが自由で様々なカバーが存在するが、熱湯を沸かさなければいけないのでやけどには注意だ。それさえ気をつければ、電化製品では味わえない心地よい温かさの省エネのアイテムだ。
近年では電子レンジで温めるだけで使えるものもあるので、そちらもおすすめだ。
③丹前(たんぜん)/褞袍(どてら)
丹前(褞袍)とは丈が長く、綿が入っているものをいう。よく「半纏」や「ちゃんちゃんこ」と間違われることが多いが、半纏は丈が短く、ちゃんちゃんこは袖のないものをいう。
この綿入れ半纏、または丹前は羽織って着る防寒着であり、江戸後期から庶民の日常着となった。幕府から絹織物を禁じられていた農民の間で木綿織物の技術がめざましく発展し、主流となった。
暖房で部屋を温めると暑くなりすぎてしまったり、ヒーターを使うのは火事が怖いなどといった人から人気であり、最近ではおしゃれ丹前として柄入りのものもある。
寒い冬を乗り越える為にはこの3つは欠かせないアイテムである。
これらは、エアコン・ヒーター・電気毛布といった電化製品に頼らずして暖を取ることが出来るためコストカットを見込めてオススメである。
下半身は股引、上着は丹前、腰回りや足元を湯たんぽで全身を温め年末を迎えるのは如何でしょうか?
参考:
綿入れはんてん・どてら豆知識
股引
湯たんぽ
丹前
フォローしていただくと、更新情報を受取ることが出来ます。