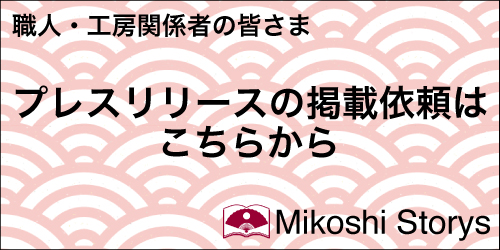東アジアを中心に使用される食に纏わる道具の一つといえば「箸」です。 二本でひとつとなった棒状のものを器用に扱い、ものを口に運ぶだけではなく 挟む、切るなど様々な用途で使います。 今回は、箸についてご紹介します。

◎語源
語源は諸説あり、その中でも最も有名なのが、 東京藝術大学美術部教授である三田村有純氏による説が最も強いと言われています。 それによると、大和言葉で物の両端や物と物との境目を意味する「ハ」、物をつなぎ止める・固定する・静止する意味をもつ「シ」を組み合わせたのが語源となります。
◎二本で「一膳」
箸の数え方は、「本」では表さず、「膳」で表します。 二本一体で「一膳」と数え、「膳」を使うには理由があります。 にくづき(月)は、体の器官を表すのに用いられます。箸は一膳で、つまむ・はさむ・押さえる・すくう・裂く・のせる・はがす・支える・くるむ・切る・運ぶ・混ぜるといった12もの機能を果たしてきた体の一部のような存在だからです。 
◎日本の箸
日本において、用いられる箸の多くは「塗り箸」と呼ばれ、短い木に漆や合成樹脂を塗ったものです。漆で塗りを重ねた箸には独特の光沢があり、和の趣があります。
他国で使用されている箸と違うのは、片端に向けて細くなっていることです。これは骨付きの魚を食べる際に、骨と身の部分を分けやすくするためです。
箸は東アジアにおいて多く使用されていますが、各国で見た目や素材が違います。
中国では、青銅製のものがかつては使用されていましたが近年は竹や木、折れにくさを重視したプラスチック製を使用することが多くなりました。朝鮮では、ステンレス製がメインで、これは王族などの階級の名残でもあります。


フォローしていただくと、更新情報を受け取ることができます。