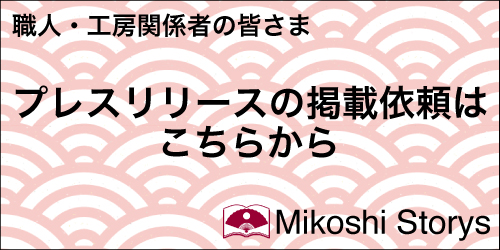東京はめっきり寒くなってきた。
友人や同僚と外食に出かける夜、人混み、駅から少し歩いて店内に入り、席を見つけてようやく腰を落ち着かせて一息、「いらっしゃいませ」と店員に、あたたかいおしぼりが渡される。とたんに冷えた指先が温まり、清潔な布に日頃の疲れまで拭われた気分になる。さあ何を食べようか。
今回は、我々にとっては身近で当たり前な、日本式のおもてなしの名脇役「おしぼり」についてご紹介する。
おしぼりの歴史:起源は平安時代から
『古事記』や『源氏物語』が書かれた時代にはもう存在していたと考えられている。客人を家に招く際に濡れた布を提供するのは、日本古来の慣習であったのだ。実際に「おしぼり」と呼ばれるようになったのは江戸時代で、宿屋の玄関に用意された水の桶と手ぬぐいを“しぼって”旅人が手や足を拭っていたのでそう呼ばれるようになった。
おしぼりの役割:心も身体もリラックス
お手拭きとして手を清潔にするのもひとつだが、それ以外にも使い道がある。人肌よりやや熱めのおしぼりは、目の上や顔に乗せると血流を良くして疲労の解消につながる。理容室で髪を洗った後に首下に暖かいおしぼりを置いてくれることがあるのはそのためだ。おしぼりで拭うことは、ただきれいにするだけでなく心的な癒しも与えてくれる。
おしぼりの品質:紙かタオルか、それも重要だ
最近では洋食のレストランを中心に、ビニールに包まれてアルコールを含んだ使い捨てのものが一般的だ。逆に、おしぼり置きがあったり、布に装飾がなされていたり、はたまた香りまで付いていたり、凝っている店では抜かりないこだわりを見せてくれる。日本では「貸おしぼり業」が発達しており、そういった専門業者が、清潔で尚且つ季節によって温度を変えたおしぼりを店に提供している。


日本食が広まってゆくのと同時に、最近では海外への広まりも見せている。もともと欧米ではナプキンしか無かったが、日本の飛行機で乗客に配られていたのが評判になり、おもてなしのひとつに取り入れられつつある。一方、中国や韓国の料理店ではいち早く広まりを見せていて、布おしぼりを提供してくれるところも少なくない。
お客様へのおもてなしの好意と共に、受け継がれてきたおしぼりの伝統。寒い冬に温かいおしぼりを渡すのは、古い歴史と素敵な効用があるからこそ欠かせない気遣いである。席につけば差し出されるというのは、ごく普通なサービスだが、それが当たり前であること自体が実は日本特有なのだ。
そんな優しい心づかいに対して「ありがとう」の一言を添えてみてはいかがだろうか。もてなす側ともてなされる側両方があたたかい気分になれるに違いない。
参考:
・東日本おしぼり協同組合
・全国おしぼり協同組合
フォローしていただくと、更新情報を受け取ることができます。